
- 第1話 「健康保険」とか「年金」て何? 初心者向け、基本中の基本を解説
- 第2話 健康保険や年金の制度って、誰が運営しているの?
- 第3話「社会保障」と「社会保険」の違いと、実はよく分からない?「社会保険」の意味
- 第4話 健康保険と年金制度の種類はどうなっている? ~加入している健康保険の見分け方~
- 第5話 経済的自立を目指す人は、社会保障についても学んだほうが良い?
- 第6話 「国民健康保険と国民年金保険ってどう違うんだぜ?」 博士が基本を解説します。
- 第7話 求人情報の「社会保険完備」、何がどう完備なの?
- 第8話 入院時に「○○認定証はありますか」と言われたら ~高額療養費、初級編~
- 第9話 社会保障と切っても切れない関係、「住民税」の基本を解説
- 第10話 マイナンバーカードがあれば健康保険証が不要になるの?(そうは行かない)
- 第11話 国民年金保険料は1か月いくら? 1か月支払うと、もらえる額はどれだけ増える?
- 第12話 お得度最強? 国民年金の付加保険料について博士が解説
- 第13話 国民年金保険料の免除・納付猶予制度とは ~上手に使えばお得な制度~
- 第14話 国民年金保険料免除申請書の書き方と、免除申請などの承認基準
- 第15話 免除された国民年金保険料の後払い(追納)について
- 第16話 年金保険料の学生特例制度(納付猶予)の対象となる「学生」とは
- 第17話 年金保険料の学生納付特例申請書の書き方、注意点について
- 第18話 名前は「免除」だが中身は全然違う、「産前産後の年金保険料免除制度」
- 第19話 出産時の、健康保険制度からの給付 ~出産育児一時金と直接支払制度~
- 第21話 国民年金保険料の払い方いろいろ ~お得な納付方法とは~
- 第22話 国民健康保険料はどんな計算で決まるのか?
- 第23話 今語ろう、真の「国民年金」の歴史を! ~年金制度は2階建て~
- 第24話 4月から6月の間に残業すると損? ~社会保険料を決める「標準報酬月額」のしくみ~
- 第25話 給与明細書を眺めてみよう ~これがあなたの社会保険料です~
- 第26話 健康保険の扶養制度について ~国保には扶養はないよ!~
- 第27話 複雑怪奇、各地でバラバラ、子供の医療費助成制度
- 第28話 国民年金制度における、被扶養者の仕組みについて ~第3号被保険者とは~
- 第29話 失業後の健康保険をどうするか ~任意継続制度について~
- 第30話 失業した場合の、国民健康保険料の減額について ~非自発的失業者軽減制度~
- 第31話「社会保険」の適用事業所とは ~加入義務のある事業~
- 第32話 「社会保険」が適用される「従業員」の条件とは ~パート社員は対象?~
- 第33話 インフレが加速すると、どんなことが起きる? ~年金生活者への影響も~
- 第34話 公的年金支給額の、物価・賃金連動の仕組みとは
- 第35話 主要都市の国民健康保険料を比較してみる
- 特別企画(1)【やってみよう】スマホのキャッシュレス決済で、税金と年金保険料を払ってみる
- 第36話 国が定める、国民健康保険料の「コロナ減免」とは
- 第37話 国民年金保険料の「コロナ特例免除」について ~所得見込額申立書の書き方など~
- 第38話 コロナの影響で事業所の休業があった場合の、標準報酬月額の特例改定とは
- 特別企画(2)【やってみよう】国民健康保険料の失業減免手続きをやってみた!
第1話 「健康保険」とか「年金」て何? 初心者向け、基本中の基本を解説
まさに超基本の記事。 病院にかかる時に必ず窓口で見せる、保険証を発行しているのが「健康保険制度」(保険証がないと病院での支払いは数倍の額になってしまう)。 国民全員が、基本的にこの健康保険制度に入らないといけません。 また、歳を取って収入がなくなったり、障害者になったり,家族が亡くなった時にお金をもらうための制度が「年金制度」。 こちらは基本的に,20歳から60歳のすべての国民が加入して、保険料を支払うことになっています。 (→第1話へ)
第2話 健康保険や年金の制度って、誰が運営しているの?
国民健康保険は各市区町村(組合が運営している例外あり)、いわゆる社会保険の健康保険(被用者保険)は各健康保険組合や共済組合、国民年金と厚生年金は国(日本年金機構が業務を委託されている)。 いずれも、制度自体を作っているのは国なので、加入者は安心して良い、という内容。(→第2話へ)
第3話「社会保障」と「社会保険」の違いと、実はよく分からない?「社会保険」の意味
「社会保障」は、健康保険や年金制度を含めて、生活保護や障がい者福祉など、国や市区町村などが個人の生活をサポートする、「セーフティーネット」と呼ばれる制度を全部含む用語。 「社会保険」のほうは「広い意味」と「狭い意味」二種類があるが、とりあえずこのブログでは、「会社に入って保険証をもらったら社会保険」(狭義)ということで当面は行く、という内容。 (広い意味では、国民健康保険や国民年金、雇用保険なども含めて、制度独自に保険料を徴収して運営する社会保障制度のことを社会保険と呼ぶ) (→第3話へ)
第4話 健康保険と年金制度の種類はどうなっている? ~加入している健康保険の見分け方~
健康保険制度の種類は、ベースとなる「国民健康保険」、会社員などが加入する「社会保険」の健康保険(「被用者保険」ともいう)、「共済組合の短期給付(公務員など)」、そして主に75歳以上の人が加入する「後期高齢者医療制度」の四種類があります。 自分がどの保険に入っているかは、健康保険証に書いてある内容で判断できます。 同じく「国民皆年金」のベースが「国民年金」で、「社会保険」の年金が「厚生年金」(公務員の共済年金なども厚生年金制度に統合) なお、就職などで保険や年金が「国民」から「社会保険」に切り替わった時は月末時点で加入しているほうの制度の分を払う、ことになります。 (同月内の加入・脱退時に例外あり) (→第4話へ)
第5話 経済的自立を目指す人は、社会保障についても学んだほうが良い?
日本の年金制度は、支払われた保険料の積み立てはわずかで、基本的には現役世代が払った保険料を使って高齢者などに支給する方式。 そのため、運用に失敗しても影響は少なく、インフレにもある程度対応できるというメリットはあるが、現役世代の負担が大きいこともあり、盤石とまでは言えない。 だから、ベースの社会保障制度についてまず押さえたうえで、自力で資産運用もするというスタイルが最も安全性が高い。 なお、年金制度よりもずっと速いペースで劣化が進んでいる(被保険者の負担が増えている)のが健康保険制度で、こちらも公的制度のみならず、民間医療保険での補完も考える余地がある。 (→第5話へ)
第6話 「国民健康保険と国民年金保険ってどう違うんだぜ?」 博士が基本を解説します。
「国民健康保険」は病院で使う保険証をもらう制度、「国民年金」は老後などにお金をもらうための制度、という基本中の基本に戻った入門向けの回。 「国民」のつく2つの制度は、会社などの「社会保険」に加入していない人が入ることになっている。 なお、就職したり退職した場合は、「国民」2制度への加入や脱退手続きが必要な場合があるので注意。 (→第6話へ)
第7話 求人情報の「社会保険完備」、何がどう完備なの?
このブログではとりあえず、「社会保険」=会社の健康保険(被用者保険)と厚生年金だ、ということにしたものの、本来は,公的医療保険や年金保険,介護保険,労災保険や失業保険(いわゆる労働保険)までの,非常に広い範囲を含む用語だ、という話が第3話で出てきました。 で、求人などで「社会保険完備」とある場合は、狭い意味の「社会保険」である健康保険と厚生年金だけではなく、労災保険と失業保険(労働保険)もほぼセットでついてきますよ、という内容。 (→第7話へ)
第8話 入院時に「○○認定証はありますか」と言われたら ~高額療養費、初級編~
病院への入院時によく聞かれる「限度額適用認定証はありますか?」という質問。 これは、医療費の自己負担(3割負担など)が、所得などで決まる上限額を超えた時にあとで戻ってくる、高額療養費制度に関連している。 事前に「限度額適用認定証」を申請して、病院の窓口で見せておけば最初から上限額までの支払いで済むため、いったん払って返してもらう、というのが省略できる。 なお、70歳以上などの場合は、所得などによっては不要(というか発行されない )場合があり、この場合は保険証や「高齢受給者証」(申請しなくても送ってくる)を見せれば上限額までで済む。 ちなみに、非課税世帯の場合は、この認定証に入院時の食事代が減額される機能がつくことがあるので、役場や組合などに訊ねてみよう。 (→第8話へ)
第9話 社会保障と切っても切れない関係、「住民税」の基本を解説
「住民税」(正確には「個人住民税」)とは、都道府県及び市区町村に払う地方税で、国の税金である「所得税」と似た部分が多い。 前年1年間の間にもらった給与や年金、個人事業の売り上げなどの収入を基に計算される。 この住民税が0円(「非課税」と呼ばれる場合もある)の世帯の場合は、社会保障制度でも有利になることが多いので、年末調整や申告は慎重に行いましょう。 もう少し詳しいことを知りたい場合は、ぜひ第9話をお読みください。 (→第9話へ)
第10話 マイナンバーカードがあれば健康保険証が不要になるの?(そうは行かない)
スマホのアプリやパソコン、セブン銀行ATMで、マイナンバーカードを健康保険証として使えるように登録する制度が本格開始された。 転職などしても保険証を変更せずに済むなどのメリットはあるが、全ての病院で使えるわけでもなく、当面は結局保険証が必要。 利用登録の方法などは、第10話本文で動画リンクをつけて解説しています。 なお、「保険証の情報までがマイナンバーで管理されるなんて」という心配はすでに無駄。利用登録しようがしまいが、すでに保険証とマイナンバーの紐付け自体はとっくに完了しているので(役所の保有する主要な情報はすでに紐づけ完了。そういう法令になっているのです)。 (→第10話へ)
第11話 国民年金保険料は1か月いくら? 1か月支払うと、もらえる額はどれだけ増える?
国民年金保険料一か月分(2022年度額・16,590円)を払うと、受給額は1年に1,620円増えます。なので、10年ちょっと(76歳まで)もらえば元が取れるという計算になります。 しかし、国民年金の受給額は、ある程度インフレに連動して動くので、長期で額を単純に比較してもあまり意味はないかも。額面だけなら5年で元が取れるようになる可能性もあります。 (→第11話へ)
第12話 お得度最強? 国民年金の付加保険料について博士が解説
通常の国民年金保険料に、月額400円だけ「付加保険料」を上乗せで払うと、老後の年金受給時に「付加年金」がついてくる。 この「付加年金」、2年だけ受給すればもう支払った全額が返ってくる(3年目以降はひたすら得になる)という、利回りでみても最強の制度。 投資と違ってリスクもない、と言いたいところだが、年金自体をもらう前に亡くなったり、もらい始めてすぐに亡くなる、というリスクがあることは考慮が必要。 また、国民年金本体と違って物価連動がないので、インフレになっても受給額は変わらず、支払った意味が事実上なかった、ということになる恐れもある。 しかし、月額400円の話なので、その辺を理解したうえでとりあえず加入しておくのがおすすめ。 (→第12話へ)
第13話 国民年金保険料の免除・納付猶予制度とは ~上手に使えばお得な制度~
国民年金保険料の納付が困難な場合の救済制度はいくつか種類があり、大きく分けて以下の通りとなっている。 1 全額免除制度 2 部分免除制度 3 納付猶予制度 4 学生納付特例制度 世帯の所得や、失業の有無によって、どの制度が利用できるかが変わるが(「学生納付特例」は当然学生限定)、うまく利用すれば保険料を全く支払わずに老後の年金をもらう、ということも可能な制度。 とにかく、単に保険料を未納で放置というのが一番まずい(財産差し押さえまであり得る)ので、積極的に相談して利用しよう。 (→第13話へ)
第14話 国民年金保険料免除申請書の書き方と、免除申請などの承認基準
ほぼ、第13話の続きの内容ですが、日本年金機構が作成している申請書の書き方見本を基に、記入の際に落とし穴になりやすい箇所などを詳しく解説しています。 こればかりは、本文のほうを見てください、ということになりますね。 なお、免除申請の承認基準については、所得計算についての知識をある程度持っている人向け。通るかどうかは役場などに聞くほうがずっと早い。 (→第14話へ)
第15話 免除された国民年金保険料の後払い(追納)について
支払を免除された保険料について、後から支払うことのできる制度というものがあり、これを「追納制度」といいます。 古い年度の分だと若干利子が付くものの、10年分遡って支払うことができますが、特に全額免除については、保険料を支払わなくても半分は支払った換算になるという有利な点もあります。 とりあえず全額免除で、失業などの苦境を乗り切った後に、追納で年金受取額を増やすか、ゆっくり検討するというのがいいでしょう。そのための免除制度だとも言えます。 (→第15話へ)
[PR] 写真がうまそう。近江牛食べたい……
第16話 年金保険料の学生特例制度(納付猶予)の対象となる「学生」とは
「学生納付特例制度」とは、所得が一定の基準以下の場合に、国民年金保険料を支払わなくても良くなる、という制度です。受給額は増えませんが「未納」扱いではなく、正式に未払いが認められるということで、単に未納を放置しておくのとは大違いのメリットがあります。 対象になる学生は、細かいレアなケースもありますが、普通に大学とか専門とかに通学する場合は大体対象になるはずです。 年金機構のサイトに対象校の一覧データ(エクセル形式)があるので、そちらを見て調べるか、一番手っ取り早いのは申請する窓口で直接聞くことですね。 [PR] (→第16話へ)
第17話 年金保険料の学生納付特例申請書の書き方、注意点について
こちらもほぼ、第16話の続きとなる内容です。 日本年金機構が作成している申請書の書き方見本を基に、記入の際に落とし穴になりやすい箇所などを詳しく解説しています。 ぜひ、本文のほうをご覧ください。 (→第17話へ)
第18話 名前は「免除」だが中身は全然違う、「産前産後の年金保険料免除制度」
出産予定日前の6週間と出産後の8週間(例外あり)については、産前・産後休業(産休)の制度があります。厚生年金と、社会保険の健康保険(被用者保険)については、産休の間の保険料は全額免除が可能で、しかも年金については全額支払った扱いとなります。 また、3歳未満の子供を養育するために育児休業(育休)を取った場合も、同じく免除の扱いが可能です。 国民年金のほうにも、免除制度があります。こちらは産前・産後のみで、期間は出産予定日の前月から4か月間(例外あり)となっています。 休業を取る必要はなく、単に出産であれば免除が可能で、社会保険と同じく全額支払ったのと同じ扱いとなります。 (→第18話へ)
第19話 出産時の、健康保険制度からの給付 ~出産育児一時金と直接支払制度~
出産に健康保険は使えませんが(例外あり)その代わりに設けられているのが「出産育児一時金」の制度で、多くの健康保険では出産一児当たり42万円となっています。 実際に出産にかかった費用とは無関係に、一律の額となっている点が特徴です。 (レアケースだが、「産科医療補償制度」という制度が適用されない場合は、1万2千円減額。また、独自に42万円に額を上乗せしている健康保険もある)。 支給に当たっては、出産した病院に直接健康保険が42万円を支払う「直接支払制度」が主流で、この場合は42万円を超えた額だけを病院に支払えばよい、ということになります。 逆に、出産費用が42万円を下回った場合は、申請により残額の支給を受けることもできます。 (→第19話へ)
第21話 国民年金保険料の払い方いろいろ ~お得な納付方法とは~
国民年金保険料の納付方法には、いくつもの納付方法があり、保険料が割引になる場合もあります。 最も割引が大きいのが口座振替による「2年前納」で、これは4月に2年分の保険料を先払いするというものです。通常の毎月引き落としよりも、16,000円近い割引になります。 他にも1年前納、6か月前納、早割(通常よりも1か月前倒しで引き落とし)がありますが、まとめて支払う額が小さいほど割引率も低くなります。 納付書による前納というものもあり、口座振替に比べると若干割引率は低くなりますが、納付書の場合は例えば1年10か月分を全納するなど、年度の途中から年度末までや翌年度末までの保険料を前納することも可能です。 なお、クレジットカードによる保険料の支払いというものもありますが、納付書払いと同じく前納の割引率は低くなってしまいます。 その代わり、カード会社によってはポイントがつく場合もあるので、確認してみましょう。(→第21話へ)
第22話 国民健康保険料はどんな計算で決まるのか?
非常にざっくりと言えば、 (1)加入している世帯の人数が増えれば保険料が増える。 (2)世帯の前年収入が増えれば保険料が増える。 (3)40歳以上から65歳未満の人が世帯にいれば、介護保険の保険料が追加でかかる。 これが国民健康保険料の仕組みということになります。 各市区町村でそれぞれに算定方式が少しずつ異なるということもあり、詳しく説明するとなかなか複雑ですが、そこは本編のほうをお読みいただければと思います。 (→第22話へ)
第23話 今語ろう、真の「国民年金」の歴史を! ~年金制度は2階建て~
自分で会社などに勤めて厚生年金に加入している人も、その扶養に入っている配偶者(夫、妻)も、みんな「国民年金」にも加入しています。 一般に「国民年金」と言えば、自分で加入して保険料を納めている人のこと、と思われがちですが、これは正確には「第1号被保険者」と言います。 一方、厚生年金の加入者は「第2号被保険者」、扶養される配偶者は「第3号被保険者」と呼ばれ、このうち保険料が一切かからない「第3号被保険者」だけは比較的名称が知られているかと思います。 このような仕組みを「基礎年金制度」といい、厚生年金は国民年金=基礎年金に上乗せされる、いわゆる「2階部分」となっています。 (→第23話へ)
第24話 4月から6月の間に残業すると損? ~社会保険料を決める「標準報酬月額」のしくみ~
いわゆる社会保険の保険料は、給与に連動して決められることになっています。 月の給与額(報酬月額)に応じて「標準報酬月額」というものが決められており、その額に一定の料率をかけた額が保険料となります。 標準報酬月額は、4月~6月の間の給与をもとに算出するのが基本です。そのため、この3か月間の給与が残業などで高くなると、保険料が高くなってしまいます。 そのため、給与額が大きく変わったような場合には、「随時改定」「保険者算定」という、再計算の仕組みがあります。 (→第24話へ)
第25話 給与明細書を眺めてみよう ~これがあなたの社会保険料です~
ファイヤ君の給与明細書を見本代わりに、給料からはどんなものが天引きされているかを見てみよう、という回。 健康保険料、厚生年金保険料の他に、雇用保険料や所得税、住民税など様々なものが差し引かれた残りが給料として振り込まれるわけなので、それらの仕組みをある程度理解しておくことは重要です。 (→第25話へ)
第26話 健康保険の扶養制度について ~国保には扶養はないよ!~
社会保険の健康保険の扶養に入れるのは、 ① 働いている本人の配偶者(内縁関係=「事実婚」も含む)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹 ② ①以外の、本人の三親等以内の親族、及び事実婚関係にある配偶者の父母や子(配偶者の死後も扶養可) となっています。 ①は本人が生計を維持していればOK、②はそれに加えて世帯が同じことが条件となります。 さらに、年間収入が130万円未満で本人の半分以下であること(いわゆる「130万円の壁」)などの条件があります。 ちなみに国民健康保険には「扶養」という考え方はなく、住民票の世帯単位での加入となります。人数単位でかかる保険料もあるので、例え被保険者が子供であっても、保険料がかかります(世帯主が支払うことになります)。 (→第26話へ)
第27話 複雑怪奇、各地でバラバラ、子供の医療費助成制度
小学校に入る前の子供については、通常3割負担となっている健康保険の自己負担が、2割負担に引き下げられています。 国としての措置はこれだけなのですが、実際には各市区町村がそれぞれ独自に子供の医療費助成制度を作っています。 対象年齢も、中学生や高校生まで対象になっている場合があり、2割(3割)負担を全くの無料にまで下げたり、あるいは一定の上限額までで済むようにしていたり、まさに千差万別。 本編では、よくある助成制度のパターンを分類して紹介しています。 (→第27話へ)
第28話 国民年金制度における、被扶養者の仕組みについて ~第3号被保険者とは~
年金制度における被扶養者を、「第3号被保険者」と言います。 同じ扶養の制度でも、第26話で解説した健康保険(被用者保険)の被扶養者とは違い、国民年金のほうは配偶者しか対象となりません。 年金制度独自の特徴として、年齢などの制限が存在します。国民年金の加入義務があるのは、20歳到達から60歳未満までの間なので 、その範囲外の年齢であれば、第3号被保険者にもなりません。 また、扶養する側である厚生年金加入者が65歳を超えた場合も、その被扶養者は第3号被保険者ではなくなる(第1号被保険者として、自分で保険料を支払うことになる)というルールがあります(一部例外あり)。 (→第28話へ)
第29話 失業後の健康保険をどうするか ~任意継続制度について~
退職などによって社会保険の健康保険から脱退した場合、国民健康保険に入るか、今までの健康保険を継続するかを選べる場合があります。 この、継続の制度を「任意継続」と言い、2か月以上社会保険に入った後に辞めた場合、最大2年間はそれまでの健康保険を継続できます。 国民健康保険とどちらを選ぶかは、保険料の額で比較するのが一般的です。それぞれ、試算を出してもらえることが多いので、具体的な金額でお得なほうを選びましょう。 なお、誰かの社会保険の扶養に入れる場合は、保険料がかかりません。これが一番有利な選択肢になるでしょう。 (→第29話へ)
第30話 失業した場合の、国民健康保険料の減額について ~非自発的失業者軽減制度~
国民健康保険料(税)の計算方法の細かい部分は、各市区町村などが独自に決めており、 どの程度の所得があれば保険料がどのくらいにかもそれぞれ異なります。 ただし、低所得者の減額制度(「法定軽減」)という仕組みと、会社都合などで失業したときの減額制度(「非自発的失業者軽減」)については、国が統一した扱いを決めているので、どこの市区町村でも共通で減額を受けることができます。 「非自発的失業者軽減」の適用を希望する場合は、「雇用保険受給資格者証」を持参して役場に申請に行くことになります。そこに記載されている「離職理由コード」によって、適用されるかどうかが決まります。 条件に該当した場合、前年の所得を7割引きした額で保険料の計算をしてもらえますので、かなりの減額が見込めます。また、高額療養費の限度額判定なども、この7割引きの所得で判定されるので、医療費も安くなるという有利な制度になっています。 (→第30話へ)
第31話「社会保険」の適用事業所とは ~加入義務のある事業~
いわゆる社会保険、被用者保険や厚生年金への加入が法的に義務化されている事業は、2種類あります。 (1)従業員のいる法人 株式会社や合同会社など、いわゆる「会社」がこれに当たります。あとは国や地方自治体などの公務員も社会保険(共済組合など)が適用になります。社長一人しか社員のいない一人法人でも加入義務ありですが、役員報酬ゼロの場合は除外となります。 (2)従業員が常に5人以上いる個人事業(ただし事業内容による) 個人事業でも、従業員が常に5人以上いる場合は、社会保険強制適用です。 ただし、飲食業、サービス業、農業、漁業などは例外で、適用除外が認められています。 これら強制適用事業所以外にも「任意適用事業所」というものがあり、従業員の半数以上が賛成した上で事業主が届け出をすることにより、社会保険適用となります(この場合、適用に反対した社員も強制加入となる)。 (→第31話へ)
第32話 「社会保険」が適用される「従業員」の条件とは ~パート社員は対象?~
社会保険適用事業所で働く従業員は、原則として社会保険に加入することになります。 パートタイム従業員については適用除外になる場合もあるのですが、適用ルールの変更が段階的に進んでいるところです。 以前は、一週間の労働時間数及び月の労働日数が、正社員の労働時間及び日数の4分の3以上であるパート社員等のみが社会保険の適用とされていたのですが、新ルールでは以下の条件を満たせば適用となります。 ・週の労働時間が20時間以上 ・雇用期間が1年以上の見込み。(2022年10月からは、「2カ月と1日以上」に拡大)。 ・賃金の月額が8万8千円以上(年収換算で106万円以上) ・学生ではないこと 新ルールが適用されるかどうかは、事業所の従業員数などによって決まります。2022年10月からは、従業員数101人以上の場合は、新ルールが適用されます。。 なお、単に「試用期間」であることを理由に社会保険を適用しないという例が見られますが、これは不適切な扱いなので注意が必要です。 (→第32話へ)
第33話 インフレが加速すると、どんなことが起きる? ~年金生活者への影響も~
世界的にはインフレの状態が普通で、我が国のようにデフレが長く続くのは例外的です。経済成長に伴う、緩やかなインフレは悪いことではありません。 問題は、2022年現在世界中で起きている、急激なインフレです。その極限の状態が「ハイパーインフレ」と呼ばれるもので、ジンバブエで起きたハイパー・インフレでは、1日で物価が倍になる状態でした。 対処として最も一般的なのは、自国通貨以外の通貨や貴金属(金やプラチナなど)に資産を分散しておくことです。 インフレ時にもっともダメージを受けるのは、サラリーマンや年金生活者です。年金の支給額は物価に連動すると思われていますが、実は物価上昇には追い付かない仕組みになっており、インフレになればほぼ確実に目減りするからです。 (→第33話へ)
第34話 公的年金支給額の、物価・賃金連動の仕組みとは
年金額の改定の仕組みは非常に複雑です。 基本的には「物価の上昇率よりも受給額の上昇率を抑える」仕組みになっていて、具体的に言うと「物価と賃金の変動率のうち、不利なほうに合わせて改定する」ということになります。 従って、物価は上がっているが賃金はあまり上がっていない、という状況では年金額は目減りします。賃金のほうに合わせるため、物価の上昇ほど額が上がらないからです。 しかも、物価のほうは前年の上昇率を使いますが、賃金は過去数年の平均なので、余計に額が上がりにくいのです。 また、賃金の上昇に完全連動するかというとそうでもなく、さらに「マクロ経済スライド」という調整がかかり、上昇率はさらに下がります。 この調整は、現役世代などの負担を抑えて、年金制度を持続させるために導入されているのですが、結果的には「物価が上がっても年金は全く増えない」状況があり得ます。 物価が上がれば年金額は増えるはず、と思っているとショックを受けることになるので、心構えはしておく必要があります。 (→第34話へ)
第35話 主要都市の国民健康保険料を比較してみる
国民健康保険料算定の基本的な考え方と、主要な13都市の実際の保険料率を一覧表で紹介しています。 また、各都市が作っている保険料試算用のエクセルシートなどへのリンク集も掲載しています。 (→第35話へ)
特別企画(1)【やってみよう】スマホのキャッシュレス決済で、税金と年金保険料を払ってみる
都道府県や市区町村によっては、地方税をスマホ決済で支払うことで、ポイント還元を受けることができます。この記事では、「au pay」の請求書払い機能を例に、スマホ決済を使って地方税を支払う手順を解説しています。 国民年金の保険料は、スマホ決済で支払うことはできませんが、ネットバンキングなどの「ペイジー公共料金支払い」という機能を使えば、銀行やコンビニなどの窓口に行かなくても支払いが可能です。こちらの方法についても一緒に解説しています。 (→特別企画1へ)
第36話 国が定める、国民健康保険料の「コロナ減免」とは
コロナの影響で失業したなどの場合、国民健康保険料が支払えないケースが出てきてしまいます。 そのような場合、保険料を減額・免除する制度が国によって作られています。 この「免除」というのはその名の通り100%の免除で、保険料を支払う必要がなくなります。 それでも、ちゃんと保険証がもらえます。デメリットは何もない、というわけです。 国の基準では、 (1)失業・廃業した世帯主の給与収入、事業収入や不動産収入(※)の見込みが、前年よりも30%以上減少している。 (2)世帯主の前年所得額が、1000万円以下。 (3)同じく世帯主の、減少が見込まれる所得(つまり給与や事業所得等)以外の前年所得が、400万円以下。 といった条件があり、完全に失業や廃業をしたのか、それとも収入が下がっただけなのかによっても、保険料の減額率が変わってきます。 また、世帯主が実際にコロナに感染し、死亡や重症に陥った場合にも、減免が受けられます。 複雑な制度ですが、詳細については第36話本編にて解説しています。 (→第36話へ)
第37話 国民年金保険料の「コロナ特例免除」について ~所得見込額申立書の書き方など~
国民年金についても、コロナの影響で収入が減ったなどの場合は、保険料の特例免除を受けることができます。 通常は前年の所得で判定される保険料の免除を、減少後の見込み所得で判定します、というもので、通常の免除の申請書以外に、「所得見込額申立書」をいうものを提出する必要があります。 本編では、その申立書の見本を見ながら、具体的な記入方法についても解説しています。 (→第37話へ)
第38話 コロナの影響で事業所の休業があった場合の、標準報酬月額の特例改定とは
通常、社会保険料は4月から6月の3か月間にもらった給料の額で決まります(詳しくは第24話で解説しています)。 しかし、その後に会社など(事業所)がコロナの影響で休業になり、給料が減った場合(休業手当も給料に含みます)は特例的に算定をやりなおして、社会保険料を下げるという仕組みが設けられています。 社会保険にも、コロナの救済措置があるというわけですね。 (→第38話へ)
特別企画(2)【やってみよう】国民健康保険料の失業減免手続きをやってみた!
国民健康保険料は前年の1月から12月までの収入額から、必要経費に当たる額を差し引いた後の所得金額によって決まります。 そのため、失業して収入がなくなってしまった後から、前年の収入で計算した高額の保険料がかかってくることになります。 そうなると、支払いが困難なケースが出てくるため、各市区町村で保険料の減免制度を定めている場合があります。 本編では、実際に役所の窓口でその減免の申請を行った際のやり取りを、会話形式でわかりやすく紹介しています。 (→特別企画2へ)
■ 記事一覧へ
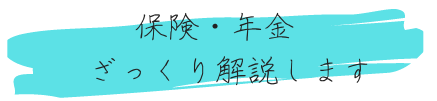


![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2c46f00d.b9410795.2c46f00e.ecaae674/?me_id=1312297&item_id=10000652&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Foumigyu-matsukiya%2Fcabinet%2Fnormal%2Fraku38_01.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
